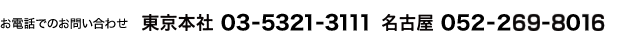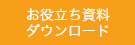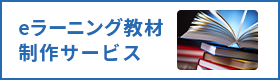2025.10.28
eラーニングで資格は取得できる?資格の例やメリットをご紹介

働きながらスキルアップを目指す方や、自宅で効率的に学びたい方の間で、近年注目を集めているのがeラーニングによる資格取得です。通学の必要がなく、自分のペースで学習を進められるため、時間や場所に制約のある社会人や学生にとって大きなメリットがあります。
本記事では、eラーニングで本当に資格が取得できるのかを解説し、取得可能な資格の例やメリット・デメリットを紹介します。さらに、資格学習におすすめのeラーニングシステムもまとめました。これから資格取得を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
1. eラーニングで資格取得できるのか
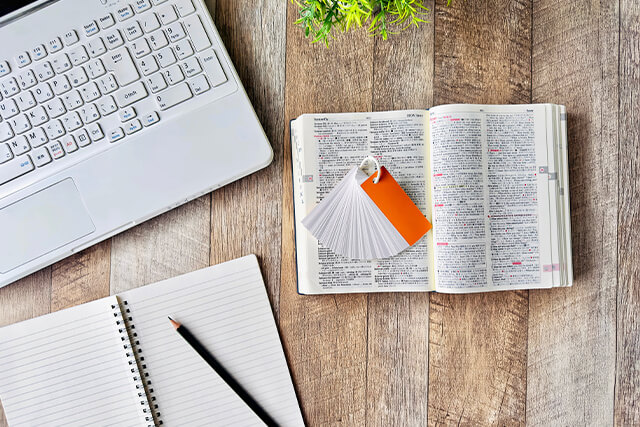
近年、「eラーニングで資格取得は可能なのか?」という疑問を持つ方が増えています。結論から言うと、多くの資格はeラーニングを通じて学習ができ、場合によっては受験や修了証の取得までオンラインで完結することもあります。
従来、資格取得といえば専門学校や資格スクールに通うのが一般的でした。しかし、働きながら学習時間を確保するのは難しく、通学のための移動や費用の負担も大きな課題でした。そこで登場したのがeラーニングによる資格学習です。インターネット環境さえあれば、パソコンやスマートフォンを使って自宅や通勤中に学習でき、限られた時間を有効に活用できます。
また、eラーニングは動画講義・テキスト教材・確認テスト・進捗管理機能などが充実しており、独学よりも効率的に学習を進められる点が大きな特徴です。最近では、国家資格や民間資格の一部でも公式にeラーニングを活用した学習が認められており、スクールに通わずとも試験合格を目指せるケースが増えています。
もちろん、すべての資格がeラーニングで完結できるわけではなく、試験会場での受験や実技試験が必要となるものもあります。しかし、筆記試験や知識習得が中心の資格であれば、eラーニングは効率的かつ現実的な学習方法として、多くの人に選ばれています。
2. eラーニングで取得できる資格の例

eラーニングを利用すれば、幅広い分野の資格取得を目指すことができます。ここでは、特に人気のある分野についてご紹介します。
IT系資格
IT分野はeラーニングとの相性が非常に良く、数多くの資格学習がオンライン対応しています。例えば「基本情報技術者試験」「ITパスポート」などの国家資格から、「CompTIA」「AWS認定資格」「MOS(Microsoft Office Specialist)」といったベンダー資格まで、多彩な学習が可能です。模擬試験や過去問題もオンラインで繰り返し挑戦できるため、効率的に合格を目指せます。
プログラミング系資格
プログラミングスキルは独学だけでは体系的な理解が難しい分野ですが、eラーニングを活用することで段階的に学べます。「Javaプログラミング能力認定試験」「Pythonエンジニア認定試験」などは、オンライン教材や演習環境が整っており、自宅でも実践的に学習可能です。資格取得と同時にスキルアップを実感できる点が魅力です。
ビジネススキル系資格
社会人に人気が高いのが、ビジネススキル関連の資格です。たとえば「日商簿記」「ファイナンシャルプランナー(FP)」「中小企業診断士」「ビジネススキル検定」などは、eラーニングで基礎から応用まで学習できます。動画講義やケーススタディを通じて実践力を養えるため、転職やキャリアアップを目指す人に選ばれています。
語学系資格
語学分野でもeラーニングは広く活用されています。「TOEIC」「英検」「中国語検定」などは、リスニングやリーディング対策をスマートフォンでも手軽に学習可能です。AIを使った発音練習やオンライン模試を提供するサービスも増えており、海外留学やグローバルキャリアを目指す人に適しています。
医療系資格
医療分野では、知識部分の学習をeラーニングで行い、実技や臨床部分は別途対面で行うスタイルが一般的です。例えば「医療事務」「登録販売者」「看護師の専門研修」「認定医」などは、基礎学習をオンラインで進められるケースが増えています。特に医療事務や調剤薬局事務などは、在宅で学習を進め、最終的な試験で資格を取得できるのが特徴です。
> 導入事例:対面での認定医試験を、Moodleを使ってオンラインでの試験実施に移行
教育・福祉系資格
eラーニングでは、教育や福祉に関する資格も取得可能です。たとえば「保育士試験」「介護研修」「メンタルヘルスマネジメント検定」などは、座学部分をオンラインで学び、実技や実習は対面で補う形が一般的です。働きながら資格を目指す人にとって、学習と仕事の両立がしやすいのが魅力です。
3. 資格取得にeラーニングを利用するメリット・デメリット
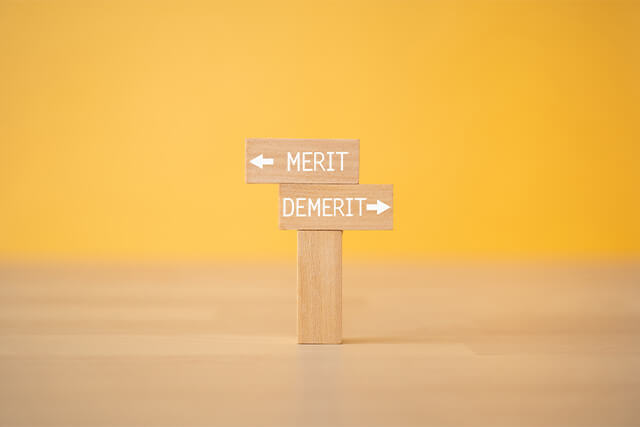
資格取得を目指す際、eラーニングを利用することには多くの利点があります。しかし一方で、注意すべき点や不向きなケースも存在します。ここでは、メリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。
eラーニングのメリット
時間や場所にとらわれない学習が可能
インターネット環境さえあれば、通勤電車の中や自宅、カフェなど、どこでも学習できます。特に仕事や家庭と両立しながら資格を目指す社会人や主婦にとって、スキマ時間を活用できるのは大きな強みです。
例:フルタイムで働く会社員が、通勤中にスマホでTOEICのリスニング練習を行う。
自分のペースで学習を進められる
通学型スクールのように決められた時間に出席する必要がなく、理解できる部分はスピーディーに進め、苦手分野は繰り返し学習することができます。
例:簿記3級の仕訳問題を、理解できるまで何度も動画講義を視聴。
費用を抑えられるケースが多い
通学型スクールと比べて、教材費や運営コストが低いため、受講料が割安に設定されていることが多いです。交通費も不要なので、トータルコストを削減できます。
最新の教材やテスト環境が利用できる
eラーニングでは、オンライン模試やAIによる学習進捗管理など、デジタルならではの機能を活用可能です。資格試験の出題傾向に合わせて教材がすぐに更新される点も魅力です。
学習記録が自動で管理される
自分で学習計画を立てるのが苦手な人でも、進捗がシステムに記録されることで「あとどれくらい勉強すればいいか」が明確になります。
eラーニングのデメリット
自己管理が必要
自由度が高い分、学習を継続する強い意志が必要です。通学型スクールのように「強制力」がないため、忙しさに流されて挫折してしまう人も少なくありません。
例:最初は意欲的に学習を始めたものの、1か月で受講を放置してしまうケース。
質問や相談がしにくい
講師や仲間と直接会う機会がないため、疑問点をその場で解決できないことがあります。多くのサービスではメールやチャットで質問できますが、回答に時間がかかる場合もあります。
実技を伴う資格には不向き
介護、看護、建築などの実技試験が必要な資格は、座学部分はオンラインで学べても、最終的に対面講習や実習が必須になります。eラーニングだけで完結できない点に注意が必要です。
通信環境やデバイスに依存する
動画講義や模試を利用する際、インターネット環境が不安定だと学習に支障をきたします。スマートフォンだけで学ぶと画面が小さく、効率が下がるケースもあります。
モチベーション維持が難しい
孤独に学習を進める形になりやすく、通学型スクールのような「仲間と一緒に頑張る」雰囲気が得にくいことがあります。
このように、eラーニングには「効率的で便利」という大きなメリットがある一方で、「自己管理力が求められる」というデメリットも存在します。どちらを重視するかを考え、自分のライフスタイルに合った学習方法を選ぶことが重要です。
> eラーニングとは? 目的から歴史、メリット・デメリット、使い方、導入のポイントまで解説!
> eラーニングを大学が導入するメリットとデメリットとは?
4. 資格取得におすすめのeラーニングシステム8選

Schoo(スクー)
社会人向けのオンライン学習サービスで、ビジネススキルから資格取得講座まで幅広く揃っています。生放送授業と録画授業があり、学習スタイルに合わせて利用することができます。特にIT系やマーケティング系の資格学習に強みがあります。
Udemy(ユーデミー)
世界最大級のオンライン学習プラットフォームです。講座数は20万以上あり、国家資格対策から専門資格、実務に直結するスキルまで幅広いジャンルをカバーしています。買い切り型なので、自分のペースで繰り返し学習できるのもメリットです。
スタディング(STUDYing)
「短期間・効率的」に資格取得を目指す学習サービスです。スマホ中心の学習設計で、スキマ時間に学べる点が魅力です。行政書士、簿記、宅建士、中小企業診断士など国家資格の対策に強い人気サービスです。
資格の大原
資格スクール大手の大原が提供するオンライン講座です。公認会計士や社会保険労務士、税理士などの難関資格をサポートしています。長年の合格実績とノウハウをオンラインでも活かせる点が強みです。
TAC(TAC WEB SCHOOL)
大手資格スクールTACのeラーニング版です。動画講義と教材、質問サポートが充実しており、ITパスポート、相続検定、年金検定、証券外務員一種、FPなど幅広い資格に対応しています。難関資格を目指す方におすすめです。
Gacco(ガッコ)
大学や企業と連携したオンライン講座プラットフォーム。無料の講座も多く、キャリアアップや学び直しに最適。資格そのものよりも、資格取得に必要な基礎知識やスキルを補う場として利用できます。
Totara Learn(トタラ ラーン)
世界的に利用されているオープンソースの学習管理システムです。高度な学習管理・研修計画・人材育成管理に強みがあります。大規模組織やカスタマイズが必要な企業向けです。大企業・公共機関の「社内資格管理」「業務必須資格(ISO・労安・セキュリティ資格)」など、大規模かつ体系的な資格教育に向いています。
> 企業向けLMS「Totara Learn」とは?人材育成に効く機能と導入メリットを徹底解説
Moodle(ムードル)
世界で最も利用されているオープンソースの学習管理システムです。豊富なプラグインやカスタマイズ性が魅力です。教育機関から企業まで幅広く利用されています。大学や専門学校での「語学系資格」「情報系資格」学習のほか、企業研修としての「ビジネス検定」「社内資格制度」にも対応できます。柔軟な運用を求める組織に最適です。
> 【Moodle基本講座】Moodleとは?
5. まとめ
eラーニングを活用すれば、忙しい社会人でも時間や場所にとらわれずに学習を進め、資格取得を目指すことができます。宅建士や簿記、IT系資格のような実務に直結するものから、キャリアアップにつながるビジネス系資格まで、対応できる領域は広がっています。
メリットとしては「スキマ時間を有効活用できる」「自分のペースで学習できる」「コストを抑えやすい」点があり、一方で「学習の継続が自己管理に委ねられる」「実技を伴う資格では対応が難しい」などのデメリットもあります。
今回ご紹介したSchooやUdemyのように手軽に学べるサービスから、資格の大原やTACのような難関資格向けの講座、さらにTotara LearnやMoodleといった企業・教育機関向けのシステムまで、用途に応じた選択肢は多様です。
自分のライフスタイルや目指す資格に合ったeラーニングを選び、学習計画を立てて取り組めば、資格取得は十分に実現可能です。ぜひeラーニングを上手に活用し、キャリアやスキルアップにつなげていきましょう。
株式会社ヒューマンサイエンスは、長年の間、認定パートナーとしてTotara LearnおよびMoodleの導入・運用を支援してきました。ご利用の際には、ぜひ弊社にお問い合わせください。
> Totara Learn導入支援
> Moodle導入支援
Moodle関連情報
- 2025.12.12
- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説
- 2025.10.28
- eラーニングで資格は取得できる?資格の例やメリットをご紹介
- 2025.10.28
- Moodle最新LTSバージョン「Moodle 4.5」とは?~主な機能と改善点を解説!
関連情報
- 2025.7.30
- 企業研修を変える!Articulate Storylineの可能性
最新ブログ
- 2025.12.18
- 製造業の教育課題をLMSで解決|教育の効率化と人材定着を支える仕組みとは?
- 2025.12.18
- 医療機関の教育課題を解決するLMSとは?導入メリットと選定ポイント
- 2025.12.12
- Vyond新機能のご紹介(2025.12)
- 2025.12.12
- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説