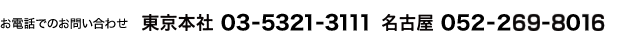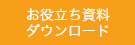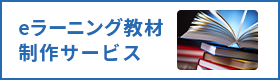2025.09.26
LMS(学習管理システム)の使い方をステップで解説~活用事例まで

社員研修や教育の現場で導入が進んでいる「LMS(学習管理システム)」。しかし、「便利そうだけれど実際にどう使うのかイメージがわかない」「導入後の活用方法が知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
このブログでは、LMSの基本から始め、使い方をステップごとにわかりやすく解説します。さらに、具体的な活用シーンや事例も取り上げ、導入後のイメージをつかんでいただける内容となっています。LMSをこれから導入・活用したい企業担当者や教育機関の方は、ぜひ参考にしてください。
1. LMS(学習管理システム)とは
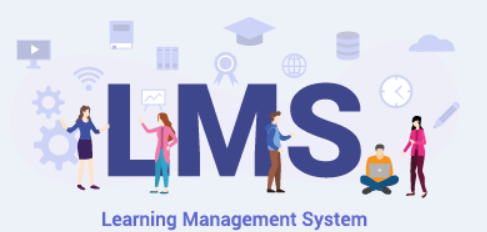
LMS(Learning Management System:学習管理システム)とは、学習や研修を効率的に運営・管理するためのプラットフォームです。教育機関や企業研修の現場で活用されており、受講者の学習履歴や成績を一元管理できることが最大の特徴です。従来は紙や表計算ソフトなどでバラバラに管理されていた学習データを、LMSを導入することでまとめて扱えるようになり、教育の質と効率を同時に高めることが可能になります。
1-1. LMSの主な機能
LMSには学習をサポートする便利な機能がそろっています。ここでは、その中から代表的なものをご紹介します。
コース管理
研修や講座を「コース」として登録・編集・公開できる機能です。受講対象者の設定や、学習期間の指定も可能で、効率的に研修プログラムを設計できます。
学習者の進捗管理
受講者ごとの学習状況をリアルタイムで確認できます。誰がどこまで学習を進めているのか、どの課題に苦戦しているのかを把握できるため、適切なフォローアップが可能になります。
教材登録機能
PDF、動画、スライド資料など、さまざまな形式の教材をシステム上に登録して配信できます。紙資料の配布やメール送信の手間を省き、受講者はいつでもアクセスして学習できます。
試験・評価機能
小テストや確認テストをオンラインで実施でき、自動採点や結果の集計も可能です。客観的な評価をスムーズに行えるため、研修成果の測定に役立ちます。
コミュニケーションツール(掲示板、チャット)
受講者同士や講師とのやり取りを促進するための機能です。掲示板やチャットを活用することで、双方向の学びや情報交換が可能になり、学習意欲の向上につながります。
>学習管理システム(LMS)とは?~基本機能から導入効果、おすすめシステムまで~
1-2. LMSの導入が進んでいる理由
近年、LMSの導入が急速に進んでいる背景には以下のような理由があります。
働き方の多様化への対応
リモートワークや在宅勤務が普及し、場所や時間に縛られない研修スタイルが求められるようになりました。LMSならオンラインで研修を完結でき、受講者の都合に合わせた学習が可能です。
研修の効率化とコスト削減
紙の資料印刷や会場手配が不要になり、担当者の運営負担や費用を大幅に削減できます。
学習効果の「見える化」
受講者の進捗や理解度を数値で把握できるため、研修の効果測定や改善に活用しやすくなります。
人材育成の戦略的活用
学習データを蓄積・分析することで、社員一人ひとりに合った育成計画を立てやすくなり、組織全体の人材育成にも直結します。
このように、LMSは教育・研修のデジタル化を支える重要な基盤として、導入が広がっています。
2. LMSの使い方をステップで解説
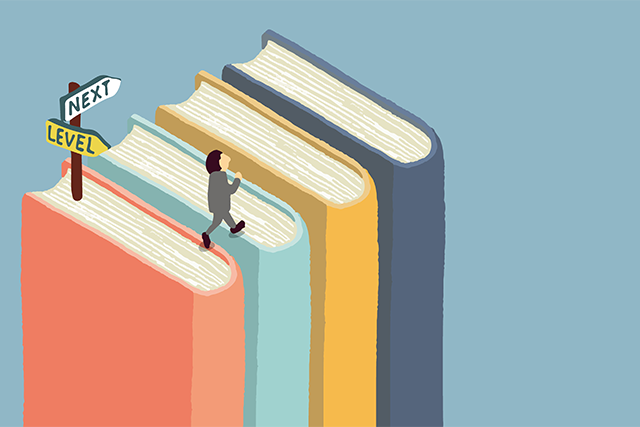
LMSを導入しても、「何から始めればいいのか」「どうやって学習者に教材を届けるのか」と迷う方も多いでしょう。ここでは、ユーザー登録、教材登録、配信という基本ステップに沿って、LMSの使い方をわかりやすく解説します。これを読めば、自社や組織でスムーズに学習管理を始めるイメージがつかめます。
2-1. 使用するユーザーを登録する
まずは「だれが学ぶか/だれが管理するか」を整えます。
基本手順
・組織・部署・役職などの属性を決める:部門・拠点・雇用区分・職種・役職・入社年など。これらの情報は、後の教材配布やレポート分析に活用できます。
・ユーザーIDの付与規則を決める:社員番号ベースを推奨(重複や変更が少なく、他システムと連携しやすい)。
・登録方法を選ぶ
→ 少数なら:管理画面から手動登録。
→ 多数なら:CSV一括登録(テンプレートに沿って氏名・メール・所属・役職などを入力)。
→ 継続運用なら:人事システム連携やディレクトリ連携で自動化。
効率化のポイント(人事システム連携)
・マスタは人事側を“正”に:入社・異動・退職を人事システムで更新し、LMSへ自動反映。
・毎日/数時間ごとに同期:配属変更や新入社員が即、正しいコースを受けられる。
・属性ルールをコースの自動割り当てに利用する:部署=「営業部」かつ役職=「主任」など。
よくあるつまずき
・氏名の全角・半角やメールの重複でインポートがエラーになる:登録前にクリーニング。
・退職者アカウントが放置される:無効化のルールを自動化して情報漏えいを防止。
2-2. コンテンツ(eラーニング教材等)を登録する
次に「何を学ぶか」を載せます。
対応する主な形式
・動画(mp4等)、資料(PDF/スライド)、Webページ、小テスト
・SCORMやxAPIパッケージ、H5P(対話型コンテンツ)など、学習履歴を細かく記録できる形式も有効。
基本手順
・コースを作成:タイトル/目的/対象/所要時間/達成基準(例:視聴100%+テスト80点以上)を設定。
・コースデザインの検討:導入→本編→確認テスト→アンケート…と学習の流れを分かりやすく。
・教材の登録:ファイルアップロード or 外部URL埋め込み。必要に応じて字幕や台本PDFも添付。
・受講要件:受講順序/必須・任意/合格基準/受講期限/再受講可否を定義。
・メタデータ&タグ:分野、スキル、レベル、対象部門をタグ化→検索性が上がりコースの割り当ても楽に。
・バージョン管理:内容更新時は版数・改定日・改定概要を明記(監査・法対応で重要)。
登録時のポイント
・再生速度の許可・続きから再生:学習体験を向上。
(資料や動画を配信する場合)ダウンロード可否を決定する:社外秘資料は閲覧のみなど権限を明確化。
・多様な受講者に対するアクセシビリティへの配慮:動画字幕の追加/代替えテキストの設定/視認性の向上など。
2-3. ユーザーにコースを割り当てる
最後に「だれに、いつまでに、どの順で」受けてもらうかを決めます。
コースの割り当て方法(代表例)
・個別割当:特定ユーザーに手動で付与。小規模・スポット研修向け。
・グループ/部署単位の割当:部門・拠点などの属性グループにコース割り当て。異動にも強い。
・ルールベースのコースの自動割り当て:
→ 例)「新入社員(入社日から30日以内)には“オンボーディング基礎”を自動付与」
→ 例)「営業部の主任以上に“コンプラ年次更新”を毎年4/1に自動付与」
・学習パス(コースの並び順/前提条件):A合格→B解放…の段階学習。
・期限・リマインド:受講期限、未了者への自動メール(〇日前・当日・超過後)
通知とガイダンス
・初回案内メール:目的/所要時間/期限/問い合わせ先を明記。
・トップページの告知。
・上長通知を有効化すると、現場でのフォローが進む。
受講後の確認
・ダッシュボードで進捗と合格率を確認:部門・役職ごとの学習の停滞ポイントを可視化。
・未了者リストを自動配信:毎週、担当者・上長へ。
・アンケート回収→改善:コース受講後の1分アンケートで継続的に品質向上。
この3ステップを押さえるだけで、日々の手作業を減らしつつ、必要な人に必要な学びを確実に届けられます。運用が回り始めたら、入社時の自動オンボーディングや年次必須研修の自動更新など、さらに自動化の幅を広げるのがおすすめです。
3. LMSの活用シーン

LMSは社員研修だけでなく、社外パートナーや顧客、さらには教育機関まで、さまざまな場面で活用されています。ここでは代表的な3つのシーンを取り上げ、具体的にどのように役立つのかを解説します。
3-1. 社内教育
LMSは、全社共通の研修から新入社員研修、階層別研修や管理職向け研修まで、幅広い層に対応できます。学習履歴や進捗状況を一元管理できるため、「誰がどの研修を修了しているか」がすぐに把握可能です。また、動画やテキスト、テストを組み合わせることで効率的に研修を進められ、現場の業務を止めることなく教育を継続できます。
3-2. 社内以外への教育
アルバイトや派遣社員などの非正規スタッフ、グループ会社や代理店、さらには顧客向けの研修にもLMSは有効です。多拠点にいる対象者へ一斉に教材を配信できるため、教育の品質を均一化できます。特に製品知識やマニュアルの共有などは、LMSを通じて迅速に周知でき、サービスの質向上や顧客満足度の向上にもつながります。
3-3. 教育機関
学校や教育サービス事業者でも、LMSは授業のオンライン化や学習サポートに広く利用されています。学生の学習進捗を把握しやすく、課題提出や試験もオンラインで管理可能です。さらに、掲示板やチャット機能を活用すれば、生徒と教員、生徒同士のコミュニケーションも促進され、学習効果を高めることができます。
>Moodleは大学だけで使われているわけではない(広範囲な利用)
>MoodleとZoomを連携してオンライン研修を行うには?
>MoodleとIBT~待合室機能を利用したオンライン試験の実施~
4. LMSの活用事例
LMSは実際にどのように役立っているのでしょうか。ここでは、企業や学会での導入事例を取り上げ、教育効果の向上や運営負担の軽減といった成果をご紹介します。
4-1. RPA活用促進のためのeラーニング導入
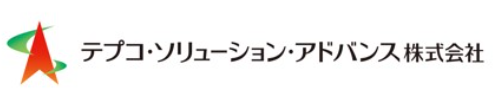
テプコ・ソリューション・アドバンス株式会社様では、業務効率化に欠かせないRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の活用を社内で推進するため、LMS「Moodle」を導入しました。
従来は対面研修や資料配布に頼っていたため、教育担当者の負担が大きく、学習者にとっても「自分のペースで学びにくい」という課題がありました。そこで、eラーニング教材を制作し、Moodle上で配信する仕組みを整備しました。
その結果、学習者は好きな時間・場所でRPAの基礎から応用まで学べるようになり、学習の定着率も向上しました。教育担当者も進捗管理を効率的に行えるようになり、全社的なスキル強化を効果的に進められています。
4-2. 救急看護セミナーをオンライン提供
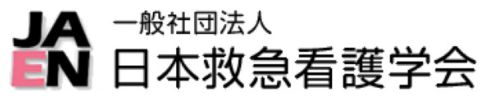
日本救急看護学会様では、専門性の高い救急看護に関するセミナーを全国の看護師に向けて実施しています。従来は会場に集まって受講する形式が中心で、参加者の移動負担や運営側の準備コストが大きな課題でした。
そこで、LMS「Moodle」を活用し、セミナーをオンライン化。さらに既存のポータルサイトと連携させることで、会員がスムーズにログイン・受講できる仕組みを構築しました。
その結果、参加者は場所を選ばず受講できるようになり、学会としても運営の負担を大幅に軽減。専門知識をより多くの看護師に届けられる環境を実現しました。
これらの事例からわかるのは、LMSは「社内の業務スキル教育」にも「専門知識の普及」にも応用できる柔軟な仕組みだという点です。自社や組織の課題に合わせて導入すれば、教育効果の向上と運営負担の軽減を同時に実現できます。
5. まとめ

LMS(学習管理システム)は、社員研修や顧客教育、教育機関での学習支援など、多様な場面で活用できる柔軟な仕組みです。ユーザーや教材を登録し、学習進捗を管理するだけでなく、コミュニケーションや評価も一元的に行えるため、教育の質と効率を大きく高められます。
実際の事例からも分かるように、LMSは教育効果を向上させると同時に、運営側の負担を軽減し、学習環境を持続的に改善する強力なツールです。
弊社では、オープンソースLMSである Moodle や、企業向けに機能を強化した Totara の導入から運用支援までをトータルでご提供しています。要件に合わせたシステム構築、教材制作、運用サポートまでワンストップで対応可能です。
自社に最適なLMSの導入を検討されている方は、ぜひ下記のサービス紹介ページもご覧ください。
関連情報
- 2025.7.30
- 企業研修を変える!Articulate Storylineの可能性
最新ブログ
- 2025.12.18
- 製造業の教育課題をLMSで解決|教育の効率化と人材定着を支える仕組みとは?
- 2025.12.18
- 医療機関の教育課題を解決するLMSとは?導入メリットと選定ポイント
- 2025.12.12
- Vyond新機能のご紹介(2025.12)
- 2025.12.12
- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説