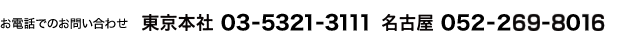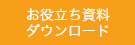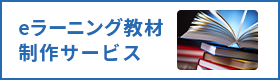2025.08.20
カスタマーハラスメント防止条例で何が変わる?企業対応と教育の全体像を解説
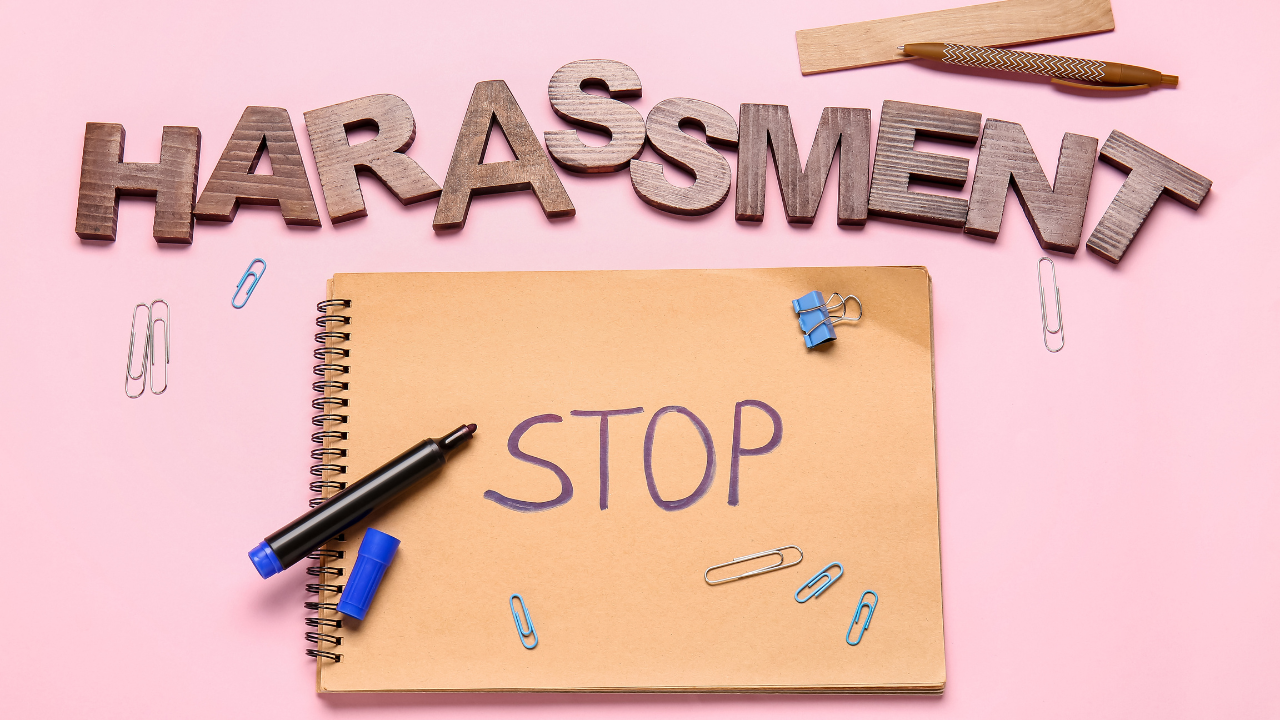
近年、顧客や取引先からの過剰なクレームや理不尽な要求によって、従業員が精神的・身体的に深刻なダメージを受ける「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が大きな社会問題となっています。とくに、2025年4月には東京都でカスハラ防止条例が施行されるなど、企業に対する対応の強化が求められています。
しかし、実際にはカスハラとはどのような行為を指すのか、どのように対応すべきかを明確に理解できていない担当者の方も多いのではないでしょうか。企業が、労務・法務の観点からの環境整備や教育体制の構築を、実質的に求められる時代が到来しています。
本記事では、カスハラの定義や背景だけでなく、法制度や条例への対応、企業がとるべき実務的な対策や教育方法まで、詳しく解説します。
1. カスタマーハラスメントとは?条例で示される視点
2025年4月に東京都で施行された「カスタマーハラスメント防止条例」では、
従業員の就業環境を著しく害する迷惑行為 を、事業者が対応すべき課題と位置づけています。
厚生労働省も「顧客等からの著しい迷惑行為」と定義しており、条例はこれを実務レベルで企業に求めています。
条例が想定する具体的な行為には、次のようなものがあります。
・正当な理由のない過度な謝罪要求
・暴言や脅迫など人格を否定する言動
・業務範囲を逸脱した不当な要求
・長時間の拘束や威圧的な態度
・SNS等を通じた誹謗中傷(いわゆる“デジタルカスハラ”)
これらは単なる「接客上のトラブル」ではなく、企業が制度として対応すべき社会的課題 とされている点が重要です。
2. カスハラが問題となっている背景
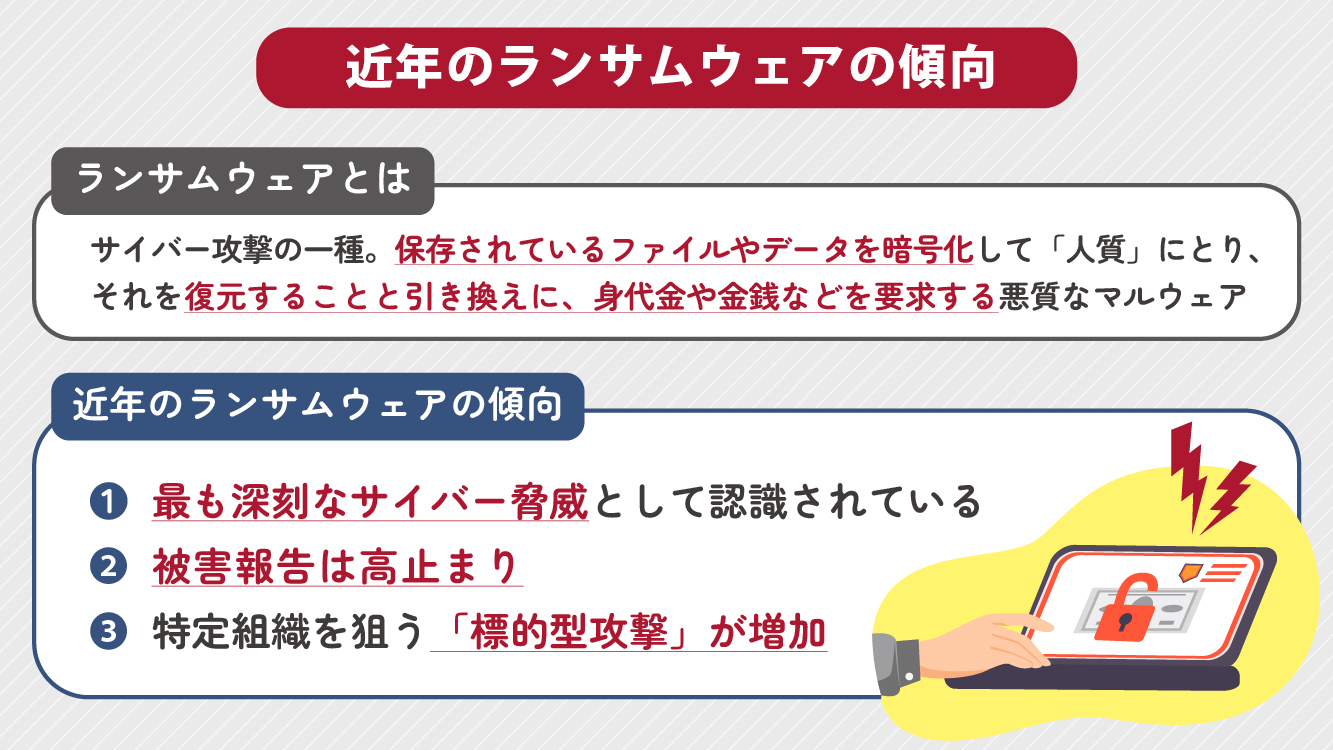
カスタマーハラスメントが問題視されるようになった背景には、労働者のメンタルヘルスへの配慮意識の高まりや、サービス業界における人手不足が挙げられます。
企業が“顧客満足”を重視するあまり、従業員に過度な対応を求めてしまう構造が、カスハラの被害を助長している側面もあります。また、インターネット上での匿名性を利用した誹謗中傷など、新たな形態のハラスメントも登場しており、対応の複雑さは増しています。
3. カスハラによる企業への影響
カスハラは、単に従業員個人のストレスだけでなく、組織全体に深刻な影響を及ぼします。
・従業員のメンタル不調や離職の増加
・職場全体のモチベーション低下
・サービス品質の低下、顧客満足度の悪化
・企業イメージの毀損や訴訟リスクの増加
特に、接客・販売・電話応対といった顧客対応が多い職種においては、早急な対策が必要です。
4. 東京都のカスハラ防止条例とは?(2025年施行)
2025年4月1日より、東京都では、全国初となる「カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されています。
この条例では、顧客等による暴言・脅迫・正当な理由がない過度な要求などの行為を禁止し、事業者にカスハラ防止のための手引作成や体制整備を努力義務として課しています。
具体的には、社内マニュアルの整備や従業員研修、顧客への注意喚起、記録体制の整備などが推奨されています。
条例に罰則規定はないものの、対応を怠ると企業の評価や信頼が低下する可能性があるため、実質的に法務・労務との連携による仕組み化を求められていると言えます。
5. 企業に求められる対応策
カスハラから従業員を守るためには、以下のような組織的な対策が重要です。
・カスハラ対応の社内ルール整備(マニュアル、指針など)・従業員からの相談窓口の設置
・管理職や現場スタッフ向けの研修・教育
・顧客に対する啓発(掲示物、HPでの案内など)
・外部機関との連携(弁護士、労務顧問、カウンセラーなど)
また、カスハラを受けた際の報告手順や記録方法を明確にしておくことも重要です。
さらに、各自治体や厚生労働省のガイドライン等に基づき対応を整備しておくと、万一の訴訟や行政指導への対策としても有効です。
特に、東京都の条例は今後全国に波及する可能性が高く、単なる接遇ルール以上の「企業責任としての対応姿勢」が問われていると言えます。
6. 教育・研修で押さえておきたいポイント
カスハラ対策を効果的に進めるためには、現場で働く従業員への教育も欠かせません。
教育では、以下のポイントを押さえておくことが重要です:
・カスハラの定義や具体例を明確に伝える
・感情的に巻き込まれないための心構え
・法的な観点から見たハラスメントのリスク
教育・研修は単に従業員の安心感を高めるだけでなく、カスハラ防止措置を実施していることを企業が示す、法制度上の対応証跡にもなります。
特に東京都の条例施行後は、実施履歴の記録や教材内容の更新も、法令遵守の一環として重要です。
7. カスハラ対策の第一歩に最適な教材をご紹介
カスハラの正しい知識を社内で共有するための教育手段として、eラーニング教材の活用は非常に効果的です。
弊社では、東京都条例にも対応した教材『STOP!ハラスメント -カスタマーハラスメントの基礎知識-』を提供しています。
本教材では、カスハラの定義や代表的な行為、判断基準、企業や従業員が取るべき対応、ケーススタディなどを約30分で学習可能です。
パワハラ・セクハラ・マタハラなどと並ぶ“新たなハラスメント”として、組織で取り組むための一歩として、ぜひご活用ください。
また、ヒューマンサイエンスでは、ビジネスマナーから生成AI活用講座まで、様々な研修教材も取り揃えています。
各社様向けのカスタマイズや多言語化にも対応していますので、ご要望などあれば、お気軽にお問い合わせください。
参考URL一覧
・厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
・東京都「カスタマーハラスメント防止条例ポータルサイト」
関連情報
- 2025.7.30
- 企業研修を変える!Articulate Storylineの可能性
最新ブログ
- 2025.12.18
- 製造業の教育課題をLMSで解決|教育の効率化と人材定着を支える仕組みとは?
- 2025.12.18
- 医療機関の教育課題を解決するLMSとは?導入メリットと選定ポイント
- 2025.12.12
- Vyond新機能のご紹介(2025.12)
- 2025.12.12
- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説